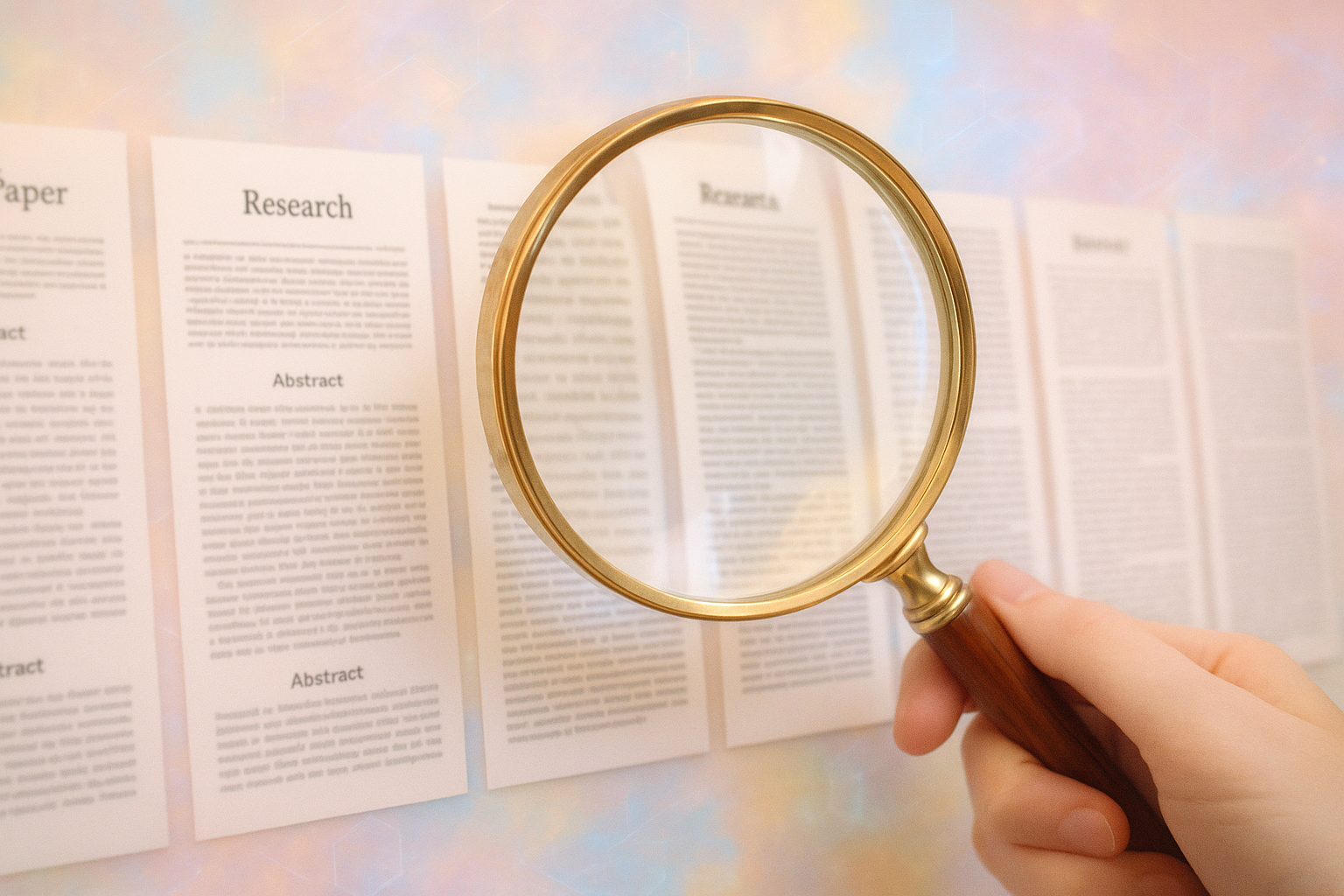この記事はこんな人におすすめ
✔ 正確で出典付きの情報を、AIで効率よく調べたい人
✔ Genspark・Perplexityなど、リサーチAIの違いを知りたい人
✔ 論文をもとにした確かな情報を、わかりやすく整理・発信したい人
WHY | できるだけフラットに正確な情報を知りたい
先日ある専門家の方から、脳科学に関するお話を伺いました。
とても興味深い内容だったのだけど、同時に難しい話でもあったので、残念ながらその場では完全に消化しきれず…。
でも後からふと、「じゃあ〇〇に関してはこういう理解で合ってるのかな?」「〇〇の場合は?」と、疑問や興味が次々湧いてきて止まりません。
だったらもうAI先生に聞いちゃおう!とうことで、今回はGensparkを使って情報を追ってみることにしました。
TRY | Gensparkを使って、リサーチAIを試してみた
Gensparkを選んだ理由
いくつかのリサーチAIサービスがある中で、今回わたしが選んだのはGenspark(ジェンスパーク)。
理由はとてもシンプルで、信頼できる情報を出典付きで提示してくれるAIだからです。
ChatGPTのように、こちらの文脈に寄り添った回答をしてくれるAIはとても便利。
でも主観を挟まず正しい情報のみを知りたいと考えたとき、その寄り添いがちょっと「パーソナライズされすぎている」感じがあったんです。何も指示しなくても、わたしに寄せすぎてしまうというか。
もちろんその寄り添いが欲しいことも多いんですが、あえて文脈の外からフラットにデータだけを拾ってきてくれる存在の力を借りたかった。
今回は複数の観点が絡み合ってひとつの事象につながっているのかどうか、そんな切り口からも深掘りしたかったんです。
こうした「複雑な問い」にも対応できるのがリサーチAIの強み。このような質問もリサーチAIならお手のものです。
AIリサーチツールといえば、Perplexityもよく名前が挙がるツール。
実際わたしも高頻度で使用していますが、情報の概要をサクッと知りたいときにはぴったりだと感じます。
でも今回求めていたのは、もう少し専門的で、根拠の明示された情報をじっくり確認したいというニーズ。
Perplexityはどちらかというとカジュアルに検索するスタイルに近くて、もう少し深く、正確に掘り下げて欲しかったんです。
そこで選んだのが、Genspark。
論文や専門性の高い難解な情報を根拠や出典付きですっきりと整理してくれる点が、今回の目的にとても合っていました。
Genspark (https://www.genspark.ai/)

Gensparkの使用感
Gensparkはとてもシンプルなページ構成です。
基本的には他のAIと同じように、チャット欄に質問や調べたいテーマを入力するだけ。
あとはAI側が複数のエージェントを使って情報を集め、まとめてくれます。

ひとつ注意点として、リサーチの完了までにやや時間がかかることがあります。
ChatGPTのように即レスがくるわけではなく、数分ほどかけてじっくり調査するスタイル。
おそらく膨大なデータベースの中から論文情報を引っ張ってきていて、その分だけ処理に時間が必要なのでしょう。
その分、リサーチ結果の信頼性や情報の密度は非常に高く、示されたデータの量も多い!
すぐ答えがほしいときというより、ちゃんと調べたいときに向いている印象です。
出力される情報の整理度と説得力
Gensparkに質問を投げると、まず最初に調査対象となる情報源が順番に表示されていきます。
ひとつひとつをちゃんと見に行っている感じで、「AIが今リサーチ中なんだな」という待機時間があるのも納得。
その分、調査された情報にはしっかりとした裏付けがある印象を受けます。
各情報源には「学術検索」「大きな文章を要約」といった表示があり、どのデータから情報を取得してるのかが視覚的にわかりやすくなっているのが特徴です。

複数の情報源を調査したあと、それらのソースをもとに複数のエージェントが連携してリサーチ結果を生成します。
最終的にそれぞれの角度(視点)からの要点をまとめた複数のブロックが作成され、いくつかのセクションにわかれて要約が表示されます。
リサーチしてもらった情報をスライドにまとめてみた
Gensparkはリサーチ機能だけでなく、スライド機能やドキュメント機能などアウトプットのためのサポート機能も備えています。
今回は、リサーチしてもらった情報をスライドにまとめてもらいました。
手順はとてもシンプルで、左メニュー内の『AIスライド』を選択し、リサーチ結果を貼り付けるだけ。
もしリクエストがあればプロンプトに追加します。
わたしは「1ページにつき、リサーチ結果の1ブロックごと」にスライドが作成されるよう指示しました。
出力されたスライドはとてもシンプルで見やすく、要点が整理された仕上がり!
ちょっとした勉強会やチーム内共有にも使えるレベル感でした。
(※内容が個人的なテーマのため、画面掲載は控えさせていただきます。)
スライドはPDF形式・PPTX形式のどちらでもダウンロードすることができます。
RESULT | Gensparkのリサーチで得られた気づき
Gensparkでのリサーチは、情報の深さ・整理のされ方・出典の明示、どれを取っても信頼感のある内容でした。
さらにスライド出力機能を使ってみたことで、「調べる」だけでなく「伝える」ところまで一気通貫でサポートしてくれることの便利さにも気付けました。
たびたびGensparkを使うことはあったけど、これまであまりうまく活用できていなかったのは、リサーチの対象がGenspark向きではなかっただけだったのかも。専門的なテーマに対しては、やはり強い!
LEARN | リサーチAIも「使い分け」がカギかも
実はGensparkと同じ内容を、ChatGPTの「DeepResearch」でもリサーチしてもらったんです。
DeepResearchとGenspark、ともにリサーチAIですが、アウトプットのスタイルや使い勝手には結構違いがありました。
Gensparkは調査対象のリソースをひとつひとつ拾いながら、複数の視点を整理して要点をブロックごとに表示してくれるため、構成がとても見やすく視覚的にも理解しやすい。
さらに、そのままスライドやドキュメントとして出力できる機能も備わっているので「調べる」から「伝える」までを一貫してサポートしてくれる便利さがあります。
一方で、DeepResearchはChatGPT内で使えるアドオン機能のような位置づけで、より論文に近いスタイルでまとめてくれるのが特長。
引用番号や参考文献の書き方などは本格的ですが、文章がやや硬くて専門的すぎる印象もあり、わたしには少し読みづらく感じました。とはいえ、このフォーマットを求めている方にとっては頼もしいはず。
こうした違いは、実際に使ってみないとわからない部分が多いもの。
だからこそ、まずは気になったツールをどんどん気軽に試してみることが大切。
さらに使い方にバリエーションを持たせることで「自分に合う使い分けのスタイル」ができてくるのかもしれません。
MEMO | Genspark活用のまとめ
即レスではなく、じっくり調査型
数分かかるけれど、出典つきで丁寧な情報を提示してくれる。落ち着いて調べたいときにおすすめ。
専門的なテーマに向いている
論文や専門データをベースにしているので、カジュアルな検索よりも「がっつり調べたい」ときにぴったり。
アウトプット機能も活用しよう
AIスライド・AIドキュメントの機能で、調べた情報をそのまま「伝える」形に整えてくれるのが便利。
無料プランでも十分試せる
無課金でもある程度のリサーチが可能。クレジット制なのでテーマを絞って使うのがおすすめ。